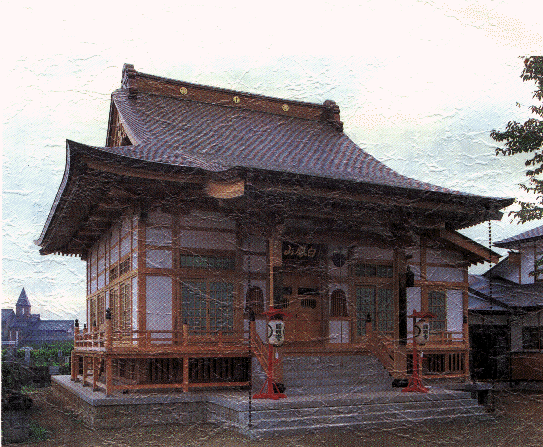
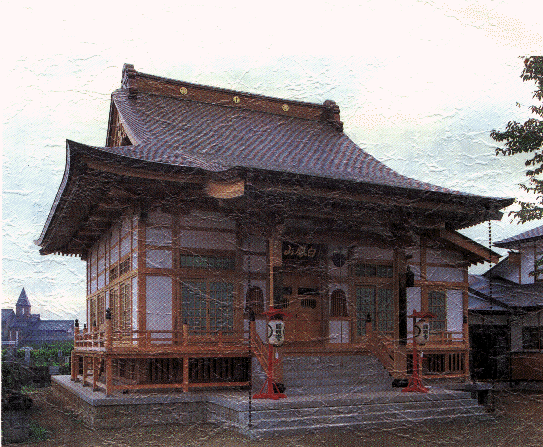
円通寺は永録元年(1558年)学心和尚によって開基されたと伝えられ、当初は村の南側にあったが、火災で焼失し、現在地には延宝年間(1673年頃)に再建されたと考えられる。
開基以来4百数十年の間には、盛衰もあったが、歴代住職の布教や壇信徒の支えによって、寺門は大いに興隆した。
本尊は、湛慶の作と伝えられる阿弥陀如来像で、火災の際も焼失を免れ、脇侍と共に今に伝えられている。また、行基菩薩の作と伝えられる馬頭観音像も安置されており、農耕馬が多く飼育されていた時代は、毎年旧4月8日の祭礼には、観音山のお堂に観音像が遷移され、近郷近在は勿論、県外からも参詣人が訪れ、終日賑わっていた。馬の少なくなった現在でも5月8日には、円通寺で例祭が行われている。
また、当時は、会津三十三観音の一つ高倉観音の札所でもあり、西国三十三観音がまつられており、8月9日の縁日には参者も多い。この他、聖徳太子像、延命地蔵などもまつられている。
更に、明治7年には本郷小学校当寺に開設され、学校教育に貢献した。また、農繁期には、季節保育所を開設するなど社会福祉にも貢献した。
このように、円通寺には古い歴史があり、地域社会で果たしてきた役割も大きい。
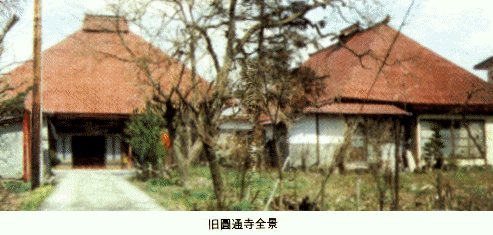
江戸時代初期の火災には仏具や古文書などの大部分を焼失したと考えられる。しかし、特に貴重な文化財は火災の際に搬出し、焼失を免れている。
町では、円通寺所蔵の重要性を鑑み、昭和49年度には、仏師湛慶の作と伝えられる本尊阿弥陀如来像、行基菩薩の作と伝えられる馬頭観音像、狩野法眼元信の筆と言われている馬の絵を逸早く町の文化財に指定し、その保護に努めている。これら3点は制作年代からみて、火災以前から円通寺に所蔵されていたものと考えられる。
その他、文化財には指定されていないが、一木彫りという古い制作法で作られた聖徳太子像(幼年像)、制作年が明記された会津本郷白磁創製の初期の作品など、貴重な遺産が残されている。また、金工品の鐘(元禄14年・1701年)や樽火鉢など、江戸時代中期のものと推定される遺産も残されている。
以上のように、円通寺は、古い歴史とそれを裏付ける多くの史料の現存する由緒ある寺である。